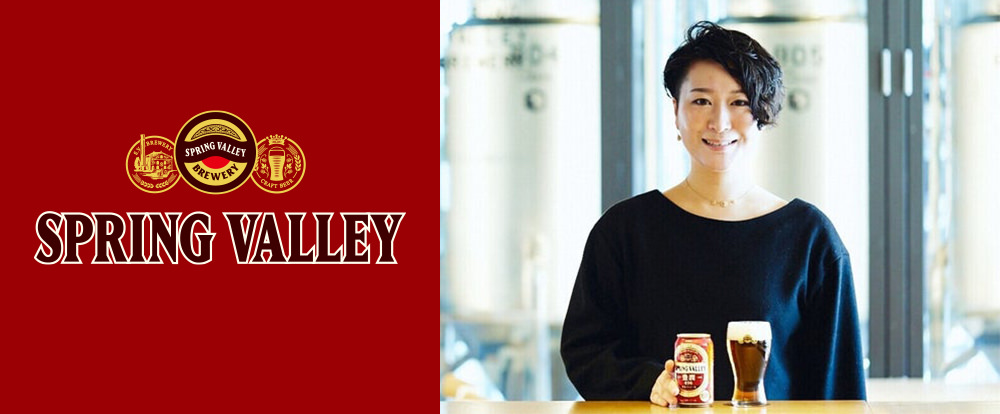
�N���t�g�r�[���������Ɛg�߂ȑ��݂ɁB�wSPRING VALLEY �L����496���x�a���ւ̑z��
2021.09.16
�u���̂܂܂��ƃr�[�����܂�Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��v
����Ȋ�@���������1�l�̏����Ј����A�N���t�g�r�[�����Ƃ̍\�z�����ŋ��ɂ��ĎВ��Ƀv���[�������̂�2012�N�̂��Ƃł����B
���ꂩ��3�N�Ԃ̍\�z���Ԃ��o��2015�N�ɁA�L�����̃N���t�g�u�������[�Ƃ��āA�㊯�R�Ɖ��l�ɁwSPRING VALLEY BREWERY�i�ȉ�SVB�j�x���I�[�v�����܂����B

�u���{�̃r�[���������A�����Ɩʔ����������v�Ƃ����M�O�ŁA����܂ł̃r�[���ɑ�����I�ȃC���[�W�����X�̌��L���ȃr�[���\���Ă���SVB�B
����Ȕނ炪�A���Ȃ钧��Ƃ��Ă͂��߂�̂��A�wSPRING VALLEY �L����496���x�̑S���W�J�ł��BSVB�̃t���b�O�V�b�v�r�[���w496�x���x�[�X�ɐi���������wSPRING VALLEY �L����496���x���A2021�N3�����S���Ŕ̔����J�n���܂����B

����10�N�œ��{�̃r�[�������͂ǂ̂悤�ɕω����Ă����̂��A������SVB���N���t�g�r�[���̑S�������Ɏ���܂ł̌o�܂Ƃ́B
SVB�����グ�̂��������ƂȂ鎆�ŋ������A�wSPRING VALLEY �L����496���x�̊J�����őO���Ői�߂Ă����g����q�ɘb���܂����B

�y�v���t�B�[���z�g����q
�L�����r�[��������� ���Ƒn�����uSPRING VALLEY�S���v
2006�N���ЁB�c�Ƃ��o����A�}�[�P�e�B���O���Ɉٓ��B�`���[�n�C��J�N�e���ȂǁARTD�ƌĂ�鏤�i�Q���肪�����̂��A�r�[���̊J���S���ցB�Г��͂������A�e�n�̏����ƂƂ��������Ȃ���A�N���t�g�r�[���헪�̗����҂Ƃ��Ċ������B���Z�Ȏd���̂������A���w���ォ�瑱���Ă��鉉�������ł��r�{���肪���Ă���B
SVB���N���t�g�r�[����S�������������R

—�g�삳�N���t�g�r�[�����Ƃɑ���z�������ŋ��ɂ��āA�В��Ƀv���[�����Ă���Ԃ��Ȃ�10�N�ɂȂ�܂��BSVB�̃v���W�F�N�g�������オ���Ă��獡�܂ł�U��Ԃ��Ă݂āA�������ł����H
�g��F�ŏ��͎��ƁA�L�����̃}�X�^�[�u�������[�ł���c�R�q�L�A�̂���SVB�̎В��ɂȂ�a�c�O��3�l�����݉�ŃN���t�g�r�[���̘b�����Ă����Ƃ��납��͂��܂�����ł���ˁB���̎��ɁA�u�r�[���̐��E���Ă���Ȃɖʔ�������A�L���������V�������Ƃ����ׂ����v�Ǝv���āB
��������SVB�̍\�z���l���͂��߂��̂ŁA�u10�N�ł悭�����܂ł����ȁv�Ƃ����C�����ł��B�����̓N���t�g�r�[�����Č��t���畷�������Ƃ̂Ȃ������قƂ�ǂł������A���ł͂����ȏꏊ�Ŏ��ɂ���悤�ɂȂ�܂������A�r�[�����X�ȊO�ł����߂�悤�ɂȂ��Ă����̂ŁB�������A�����������S������Ă����Ƃ͎v���Ă��܂��A10�N�ł�����������ɂȂ����͖̂{���ɂ��������Ƃ��ȂƎv���܂��B
—�u���{�̃r�[���������A�����Ɩʔ����������v�Ƃ����z���Ŋ������Ă����Ȃ��ŁA���܂��܂ȉۑ���������Ǝv���܂��B�ǂ�Ȃ��Ƃ��ӎ�����SVB�𐬒������Ă����̂������Ă��������B
�g��FSVB���ŏ��ɂ��ׂ����Ƃ́A�u�r�[���̎�ނ́A�W���b�L�ɓ��������F�����ݕ���������Ȃ��v�Ƃ������Ƃ�m���Ă��炤���Ƃł����B
�Ȃ̂ŁA�Ԃ��F�������wJAZZBERRY�x�Ƃ����t���[�c�r�[���^�C�v����������A���t���̃O���X�Œ����肵�āA�r�[���̑��l����`���邱�Ƃ��ӎ����Ă��܂����B���̌��ʁA���ݔ�ׂ��y����ł��������ASNS�Řb��ɂ��Ă����������肷�邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B

�g��F����ŁA�u���������ނ������Ă��A�m�����Ȃ��ƑI�ׂȂ��v�Ƃ������ӌ�����������ł��B
���C���ł��A�Y�n��u�h�E�̕i��Ȃǂ̓�����m��Ȃ��ƁA�D�݂̂��̂�I�Ԃ̂��ē������Ȃ��ł����B����Ɠ����悤�ɁA�r�[�������ꂼ��̓�����c�����Ă��Ȃ��ƁA�����D�݂̂��̂͑I�ׂȂ��̂ŁB
���H�X�ł���A���X�̕��ɕ����Ȃ���I�Ԃ��Ƃ��ł���̂ŁA���������R�~���j�P�[�V�����ɂ���ăN���t�g�r�[�����L�����Ă����������͂���Ǝv���܂��B
�����ǁA�����Ɛg�߂ȏꏊ�ŁA�L���N���t�g�r�[�������܂���Ԃ�ڎw���Ƃ��ɁA����ς�I�ѕ�������Ƃ������͔����Ēʂ�܂���B������A�u�N���t�g�r�[���ɂ͑��l��������v�Ƃ������ƂƁA�u������Ƃ��l���Ȃ��Ă��r�[���Ƃ��Ă��������v�Ƃ������Ƃ��ɓ`���Ă����K�v������ȂƎv���Ă��܂����B

—�u�m�����Ȃ��ƑI�Ԃ̂�����v�Ƃ����ǂ����z���āA�u��ʓI�ɂ��C�y�Ɋy����ł��炦��I�����ɂ���v�Ƃ����ڕW�̂��߂ɊJ�����ꂽ�̂��A�ʂőS���������ꂽ�N���t�g�r�[���wSPRING VALLEY �L����496���x�������Ƃ������ƂȂ�ł����H
�g��F�����ł��ˁB���Ƃ��ƃN���t�g�r�[�����ʂŏo���Ƃ����C���[�W�́A10�N�O��SVB�\�z�i�K���炠������ł��B
�܂��͑�1�i�K�Ƃ��āA���c�X�Ƃ������q�l�Ƃ̐ړ_�������āA�r�[���ɂ͂�������̎�ނ�����Ƃ������Ƃ�`���Ă������Ǝv���܂����B��2�i�K�Ƃ��ẮA�e�n�̃N���t�g�u�������[����Ǝ��g��ŁA���ʂ̈��H�X����ł��N���t�g�r�[�������߂��Ԃ�ڎw���Ă��܂����B�����āA��3�i�K�Ƃ��āA�ƒ�ł����܂��܂ȃN���t�g�r�[����I�ׂ�悤�ȁA�V�������{�̃r�[�������������Ă������ƍl���Ă�����ł��B
—�Ȃ�قǁB�ʂ̃N���t�g�r�[���́ASVB�̗����グ��������\�z�ɂ�������ł��ˁB
�g��F�͂��B���m�Ȏ��������߂Ă����킯�ł͂���܂��A����10�N�̊Ԃɂ��܂��܂����]�Ȑ܂������āA2���ځA3���ڂݏo���^�C�~���O���l���Ă��܂����B�����3���ڂݏo�����Ƃɂ��āA�Г��ł��u�Ȃ����̃^�C�~���O�ŁH�v�Ƃ����c�_�͂�������ł��B�����A���ꂪ�����Ȃ̂��͎��ɂ��킩��܂���B
—�ǂ����āA���̃^�C�~���O�œ��ݐ����̂ł��傤���H
�g��F���q�l������ԋ��߂Ă����Ȃ����A�Ǝv��������ł��B�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŁA�Ƃł�������Ƃ����������̂�H�ׂ邱�ƂŋC���]��������A���ʂȎ��Ԃ����������Ƃ������C���������܂��Ă����Ȃ����ȂƁB��������A�������N���t�g�r�[���̏o�Ԃ��Ǝv������ł��B������A�N���t�g�r�[�����ʂŏo���Ȃ獡�����Ȃ��Ȃ��āB
�wSVB��10�N���l�܂����wSPRING VALLEY �L����496���x

—�ȑO�A�g�삳��́u���̃r�[���͍H�Ɛ��i�̂悤�Ɏv���Ă���Ƃ��낪����B�����ǁA�r�[���͂����Ɣ_�Ƃɒ������Ă�����̂ŁA�n���ȍ�Ƃł����Ă���B���������{���̃r�[���̖��͂�SVB�ł͓`���Ă��������v�Ƃ���������Ă��܂����B���������X�^���X�ɋ������Ă������������q��������������Ǝv���܂��B
�������A�ʂŃN���t�g�r�[�����o���Ƃ����̂́A�܂��H�Ɛ��i�̂悤�ȃC���[�W�ɋߕt���Ă��܂��Ƃ������O�����邩�Ǝv���̂ł����A���̂�����͂ǂ����l���ł����H
�g��F�����ł��ˁB�ʂɂȂ����r�[�ɑ�ʐ��Y�̍H�Ɛ��Y�̂悤�Ȉ�ۂ���������������������Ǝv����ł����ǁA���͂ł��ˁA�ʂƂ����͍̂ł��r�[���̕i����ۂĂ�e��Ȃ�ł��B
—�͂��A�����Ȃ�ł��ˁB
�g��F�r�[���͌��Ɏア�̂ŁA�r���ƈÂ��Ƃ���ŕۊǂ���K�v�������ł��B�ł�����A���������r�̃r�[����̔�����Ƃ��ɂ́A���ɓ���āA��������Ȃ���Ԃł��͂����Ă��܂����B��������������������̂ŁA�i����ۂ��Ȃ���A���L�����ʂ�����Ƃ������Ƃ��l����ƁA�ʂƂ����e�킪�x�X�g�Ȃ�ł���ˁB
�ʂň��ނƂ��������Ȃ��Ƃ��������������܂����A����͊ʂ��璼�ڈ��ނ��炾�Ǝv���܂��B�O���X�ɒ����ƍ���������āA����ɂ�����������ł���������͂��ł��B�r�ɂ͌����ڂ����i�����Ƃ����悳������܂����A�ŋ߂ł́A�i���ێ��̊ϓ_����A�N���t�g�r�[���ł��ʂŔ̔�����Ă�����̂������Ă��ł���B
—������������ɂȂ��Ă��Ă��ł��ˁB���g�́A����܂�SVB�ł����Ă����woriginal 496�x�ƕς��������͂���܂����H
�g��F���g�Â���ɂ��ẮA���܂łƂ܂������ς���Ă��܂���B���ς�炸�����ϐ������āA�z�b�v�����ĂƂ����n���ȍ�ƂŃr�[���������Ă��܂��B���������ςݏd�˂����������炱���A����悤�₭�ʂőS����������N���t�g�r�[���Ƃ����������ŁwSPRING VALLEY �L����496���x������������ł��B

�g��F���@�ł����ƁA�N���t�g�r�[���ɑ���L�����̎��g�݂́A10�N�O�Ƀf�B�b�v�z�b�v���@���J���������Ƃ���͂��܂��Ă��܂��B���Ƃ��ƃL�����ł́A������������A��n��������A���܂��܂ȃz�b�v�̎g�������������Ă��܂����B���̂Ȃ��Ő��܂ꂽ�̂��A�f�B�b�v�z�b�v���@��������ł��B
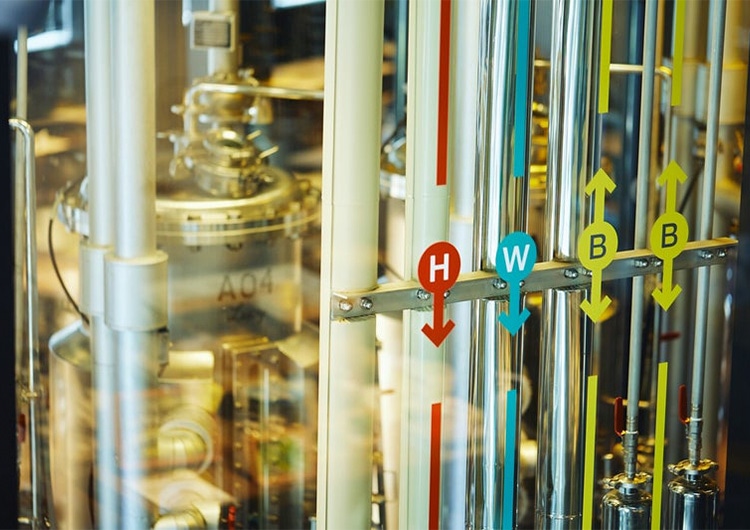
�g��F�h���C�z�b�s���O�Ƃ����̂́A�r�[��������Ō�̍H���Ńz�b�v��Ђ����ނ��ƂŁA��������������o�����@�ł��B����ɑ��āA������ύ���Ŕ��`������A�d���ݍH���̍Ō�̒i�K�Ńz�b�v�𓊓�������@�����C�g�z�b�s���O�Ƃ����܂��B������̓}�C���h�Ȏd�オ��ɂȂ�܂��B
�f�B�b�v�z�b�v���@�Ƃ����̂́A���̒��ԂŔ��`�����y���͂��߂�^�C�~���O�Ńz�b�v�����鐻�@�Ȃ�ł��B��������ƁA�}�C���h�����ǂ�������ƃz�b�v�̍��肪�����r�[���ɂȂ�܂��B
—�����̓��������������A�����Ƃ��ǂ�̐��@���Ă��ƂȂ�ł��ˁB
�g��F���������ڎw���Ă���̂́A���ƈ��݂₷�������˔������r�[���Ȃ̂ŁA��������邽�߂ɂ͍œK�Ȑ��@�Ȃ�ł��B���̃f�B�b�v�z�b�v���@���ł������Ƃ��A�L�����̃N���t�g�r�[���J���̑��|����ɂȂ�܂����B�woriginal 496�x��A����܂�SVB�Ŕ������Ă����N���t�g�r�[���ɂ��A���̐��@���g���Ă��܂��B
�L�����̍l����Z�p�����f���ꂽ�N���t�g�r�[��

—�wSPRING VALLEY �L����496���x�̋�̓I�ȓ����ɂ��ċ����Ă��������BSVB�̃t���b�O�V�b�v�r�[���ł���woriginal 496�x�Ƃ́A�ǂ̂悤�ȈႢ������̂ł��傤���H
�g��F�����܂Łworiginal 496�x�̐i���`�ł͂����ł�����ǂ��A���Ƃ��Ƃ̃o�����X�̂悳�ɉ����A���ݎn�߂̂�������Ƃ������̂��܂݂ƌ㖡�̑u�₩�������Ă��܂��B�ЂƂ������u�ԂɖL�����������Ă��炦�閡�킢�ŁA�㖡�͂Ȃ�ׂ��������肳���܂����B
�Ƃł̐H���́A���H�X�̗��������D�������t������������Ȃ��ł����B�����������ň��ރN���t�g�r�[�����l�����Ƃ��ɁA����ς���ݎn�߂ɂ������芴���锞�̖��킢�Ŗ������͂ق������ǁA��݂̋����㖡�͍����ɂ��������ȂƎv���āB�Ȃ̂ŁA�㖡���������肳���āA�A���R�[���x����0.5%���������܂����B
—�Ȃ�قǁB�ƒ�Ŋy���ނ��Ƃ��ӎ�����Ă����ł��ˁB
�g��F�͂��B���Ƃ́A�z�b�v�̕i����ς��Ă���܂��B�woriginal 496�x�ł́A�u���{�[�z�b�v�Ƃ��������I�ȃz�b�v�𗧂����Ă�����ł����ǁA���������o�����X���悭���邽�߂�4��ނ̃z�b�v��g�ݍ��킹�܂����B�H�ꂩ�炷��Ƃ�������Ԃ̂������ƂȂ�ł����ǁA�wSPRING VALLEY �L����496���x�ɂ͌������Ȃ��v�f������Ƃ������Ƃł���Ă��������ł��B

—�wSPRING VALLEY �L����496���x�Ƃ����l�[�~���O�́A�ǂ̂悤�Ɍ��߂��̂ł��傤���H
�g��F�܂��ASVB�ɂƂ��Ẵt���b�O�V�b�v�ł���woriginal 496�x�̃R���Z�v�g�������p���ł��邱�Ƃ�\�����悤�Ǝv���܂����B496�Ƃ����̂́A1����31�܂ł̐����𑫂������ŁA��1��������ł��O���Ȃ��r�[�����Ƃ����Ӗ������߂��Ă����ł��B
�����A���ꂾ���ł̓r�[���̌����`���ɂ����̂ŁA���킢�̓����ł���L���Ƃ������t�������܂����B
—�[�݂̂���ԐF�̃p�b�P�[�W����ۓI�ł��ˁB
�g��F���̐F�͓��{�Ńr�[���������L�߂邽�߁A1870�N�ɉ��l�őn�Ƃ����X�v�����O�o���[�E�u�������[�̃��S����Ƃ�܂����B�p�b�P�[�W�̒����ɕ`����Ă��郁�_���́A��������̃X�v�����O�o���[�E�u�������[�̃��x�������`�[�t�ɂȂ��Ă��܂��B

—����܂�SVB�ł́A�L��������̂ł���Ƃ������Ƃ����܂�ϋɓI�ɑł��o���Ă��܂���ł������A�wSPRING VALLEY �L����496���x�̃p�b�P�[�W�ɂ́uKIRIN�v�̕����������Ă܂���ˁB�����ɂ͂ǂ��������Ӑ}����������ł����H
�g��F�ŏ���SVB�̓X�܂𗧂��グ���Ƃ��ɁA�L�����Ƃ������O�����Ȃ������̂́A�L�����̃r�A�z�[�����Ǝ~�߂��邱�Ƃ����O���Ă�����ł���ˁB�܂����̒��I�ɂ́A���܂�N���t�g�r�[�����m���Ă��Ȃ������̂ŁB
��X�Ƃ��ẮA������������ςȂ��ɗ��Ă��������āA�u����ȃr�[��������v�Ǝv���Ă��炢�����Ƃ����C�������������̂ŁA�L�����Ƃ������O���g�킸�ɂ���Ă��܂����B
�����A�N���t�g�r�[�����L���m����悤�ɂȂ����̂ŁA��X�̃X�^���X�������ς�����ł��B�Ȃ����Ƃ����ƁA�N���t�g�r�[�����ĒN�������Ă��邩���������厖�Ȃ�ł���ˁB
—����肪������Ƃ������Ƃ��B
�g��F�͂��A�����ł��B�N���t�g�r�[�����āA�����̊炪������r�[���Ȃ�ł���B������A�ŏ��͐���ςȂ��Ɉ���ł����������߂ɃL�����Ƃ��������O���܂������A�N���t�g�r�[���S�̂̔F�m���L�����Ă������́A�L�����r�[���̍l����Z�p�ɍ��������u�������[���Ƃ������Ƃ��A��������`���Ă������Ƃ������ƂɂȂ�܂����B
—�Ȃ�قǁB���܂ŃL�������ςݏグ�Ă����Z�p��M�������A�wSPRING VALLEY �L����496���x�Ƃ����r�[���̒��ɂ����߂����Ă��ƂȂ�ł��ˁB
���{�ɃN���t�g�r�[�����������t�����߂�

—�wSPRING VALLEY �L����496���x�̔����́A���{�̃r�[��������ʔ����������Ƃ����ڕW�Ɍ������R�X�e�b�v�ڂƂ̂��Ƃł����A�g�삳��͓��{�̃N���t�g�r�[��������ǂ��Ȃ��Ă����Ăق����Ǝv���Ă��܂����H
�g��F�N���t�g�r�[�����āA�킴�킴���̓y�n�ɍs���Ȃ��ƈ��߂Ȃ��̂����͂ł���A�n�[�h���ł�����Ǝv����ł��B�����ǁA��X�̂悤�Ȋ�Ƃ��A���������̓X�܂ł������߂Ȃ��N���t�g�r�[�������葱����̂́A�����Ƃ��Ă�����ƈႤ��Ȃ����ȂƁB��������N���t�g�r�[���Ƃ������̂��A�L�߂Ă������Ƃɖ�ڂ�����Ǝv���Ă��܂��B
�Ⴆ�A�wSPRING VALLEY �L����496���x�����������ŃN���t�g�r�[����m���������A���̖ʔ����ɋC�Â��āA���̃u�������[�̃r�[��������ł݂悤���Ďv���Ă��ꂽ��������B�������������������Ƃ����Ӗ��ł��A�N���t�g�r�[�����L�߂邱�ƂɈӋ`������Ǝv���Ă��܂��B���ł��ǂ��ł����������N���t�g�r�[�������߂���A�K���̑��ʂ͑����邶��Ȃ��ł����B
—�����ł��ˁB��y�ɂ��������N���t�g�r�[������ɓ���悤�ɂȂ�����������ł���ˁB
�g��F���H�X�ł��N���t�g�r�[�����I�ׂ邵�A�Ƃł��C�y�Ɉ��߂�B����������ԂɂȂ��ď��߂āA�����Ƃ��č��t�����Ƃ�����Ǝv����ł���ˁB
���C���̗��j��U��Ԃ��Ă������ł��B�̂̓��{�ł́A���C�������ޏK��������܂���ł�����ˁB���ꂪ����ƈ��H�X�ň��܂��悤�ɂȂ�A�����ɂ͐ԁA�����ɂ͔��Ƃ����킩��₷���y�A�����O���L�܂�A�X�[�p�[�Ŏ荠�Ȃ��̂��獂���Ȃ��̂܂Ŕ�����悤�ɂȂ��āA�Ƃł�����I�Ɉ��܂��悤�ɂȂ�܂����B����͂������C�����������{�ɍ��t�����Ƃ����܂���ˁB�����l����ƁA�N���t�g�r�[�����āA��������܂���O�ɂ���Ǝv����ł��B

�g��F�N���t�g�r�[�������{�ɍ��t�����߂ɂ́A���H�X�ł��������r�[���Əo��邱�ƂƁA�Ƃł����݂����Ǝv�������ɃA�N�Z�X�ł���ꏊ�ł������Ă���Ƃ������Ƃ̗��ւ��K�v�ł��B
������A��������SVB�̓X�܂�^�b�v�}���V�F����ʂ��Ă��������N���t�g�r�[������邱�ƂƁA�ʂōL�߂Ă����Ƃ������g�݂𗼗������Ă��������ȂƁB
�������A���̂��߂ɂ͎��Ђ̐��i�����ł͂��߂ŁA�����ȃr�[�������邩�炱���A�����Ƃ��čL�����Ă����ƍl���Ă��܂��B
���^�b�v�}���V�F�F�S���̈��H�X�֓W�J���Ă���N���t�g�r�[���f�B�X�y���T�[�̒T�[�r�X
—��������ď��X�ɃN���t�g�r�[���������L�����Ă����̂́A���ޑ��Ƃ��Ă��y���݂ł��ˁB
�g��F�����ƁA����������ԂɂȂ��Ă����Ǝv����ł��B�̂͋������̃��j���[���āA�Ē��Ƃ��A�ԃ��C���Ƃ���������Ă��Ȃ������ł����ǁA���͂��ꂼ��̖����܂őI�ׂ�悤�ɂȂ��Ă��邵�A�n�C�{�[�������ĉ���ނ��������肷�邶��Ȃ��ł����B���ׂĂ̂����͑��l������h���ɂ���̂ŁA�r�[���������Ȃ��Ă����Ǝv���Ă��܂��B
�������A�r�[���̏ꍇ�́A���Ƃ��Ƒ��l������������ł���B���[���b�p�ł́A�X���Ƃɂ��܂��܂ȃX�^�C���̃r�[���������Ă��܂����B�����Ƀs���X�i�[�Ƃ������l�E�P����r�[��������āA���E��Ȋ������킯�ł���ˁB����ɂ���āA���̃r�A�X�^�C���������ɂ����Ȃ��Ă��܂�����ł��B�����ǁA�܂����l���̂����Ԃɖ߂��Ă������ꂪ���Ă�������͂���܂��B
—���Ƃ��Ƃ̑��l�������߂��āA�r�[���̖ʔ������Ĕ�������悤�ȗ���ɂȂ��Ă��Ă���ƁB
�g��F���������Ă��܂��B���������Ȃ��ŁA�u�ł�����ς�W���b�L�̃r�[��������������ˁv�Ƃ����Ĕ���������̂��A����͂���Ŋy�����Ǝv����ł���ˁB
—�Ⴄ�i�F���������炱���A���Ƃ̂Ƃ���ɖ߂��Ă����������ς���Ă�����Ă��Ƃ́A�����Ƃ���܂���ˁB
�g��F�����ł��ˁB��������ăN���t�g�r�[���������L���Ă������ƂŁA���܂�SVB���������Ă����������t�@���̕��Ɍ����Ă��A���Ԃ������������Ă����z���������ł��B

—���Ȃ݂ɁASVB�̗����グ��������N���t�g�r�[����������{�ɍL�߂�Ƃ����e�[�}���������ɂ��ւ�炸�A�Ȃ��ŏ�����ʂł̔��������Ȃ�������ł����H
�g��F�����́A�ʃr�[�����Ă����͓̂��{�ň�ԃ��W���[�ȃ^�C�v�ł���u�s���X�i�[�v�̖���������̂��Ƃ����l������������������ł��B���̓L�����ł����܂łɃs���X�i�[�ȊO�̃r�[�����ʂŏo�������Ƃ���������ł����ǁA�u����A����r�[������Ȃ��B���������Ă�́H�v�݂����Ȕ����������āB������A�N���t�g�r�[���ɂ͂����Ȏ�ނ�����Ƃ����F�m���l������܂ł͊ʂł̔̔��͓���ƍl���Ă�����ł��B
—���������������������A�ŏ��ɓX�܂������āA�����ŃN���t�g�r�[�������Ƃ����͕̂K�v�ȃX�e�b�v��������ł��ˁB
�g��F�����ł��ˁB������A�܂��͈��H�X��ʂ��ăN���t�g�r�[����m���Ă��炢�A�F�m���L�������Ƃ��ƂŁA�悤�₭�ʂł̔������ł���ƍl���Ă��܂����B����͂���ɁA�ǂ��̔����ɍs���Ă��A�F�X�Ȏ�ނ̃N���t�g�r�[�������ʂɔ�����Ƃ�����Ԃɂ������Ǝv���Ă��܂��B

SVB�̃t���b�O�V�b�v�r�[���ł���woriginal 496�x�̂����������Ȃ���A��育�ƒ�ň��݂₷�����܂�ς�����wSPRING VALLEY �L����496���x�B�ЂƂ������u�Ԃ̖L�����Ƃ�������Ƃ����㖡���y���߂܂��B���Ђ��ܖ����������B
��DRINX�ł́wSPRING VALLEY �L����496���x�̔���330ml�т�݂̂ƂȂ�܂��B�܂��A�woriginal 496�x��330ml�т�ɂĂ��������߂��������܂��B
KIRIN����note���]��
note�L���͂�����
���F��������
�ʐ^�F�y�c��
