
日本庭園とワインづくりの共通点は“無作為の作意”-植彌加藤造園 加藤友規×シャトー・メルシャン 安蔵光弘【前編】
2018.11.15
「フィネス&エレガンスのあるワイン造りとは?」の問いに、「あなた方は日本人なのだから、日本庭園のようなワインを目指しなさい」。醸造アドバイザーだったポール・ポンタリエ氏が遺したこの言葉をたよりに、理想のワインを追い求めているシャトー・メルシャン。その答えを見つけるため、京都南禅寺御用庭師を170年務める植彌加藤造園 代表取締役社長 加藤 友規さんに、チーフ・ワインメーカー安蔵 光弘が会いに行き、日本庭園の伝統、技術、哲学を伺いました。ともに自然と向き合い、“日本”を表現してきたふたりによる対談です。初秋の京都・南禅寺畔に佇む名園、無鄰菴にて。

加藤 友規
植彌加藤造園株式会社代表取締役社長。創業寛永元年(1848年)、初代加藤吉兵衛が大本山南禅寺の御用庭師を務めて以来、洛東鹿ケ谷の地にて代々造園業を営む。常に理想的な庭の状態を探求して「庭を育成」していくこと、伝統技術を活かし、時代に沿った造園空間を創造する。

安蔵(あんぞう) 光弘
シャトー・メルシャン チーフ・ワインメーカー。1995年東京大学大学院応用生命工学専攻(応用微生物学) 修士課程修了後、メルシャン入社。シャトー・メルシャン配属。2001年ボルドーのシャトー・レイソン出向。同年ボルドー第2大学醸造学部にてテイスティング適正資格(DUAD)取得。レ・シタデル・デュ・ヴァン国際ワインコンクールの審査員を3回務めるなど、海外でも経験を積み、2015年現職に就任。
ターニングポイントとなったアドバイザーの教え

安蔵光弘(以下安蔵):今日はありがとうございます。まずは私たちの紹介をさせてください。メルシャンは、1877年に設立された日本最初の民間ワイン会社である「大日本山梨葡萄酒会社」を源流にしたワインメーカーで、その中でも日本産のブドウから造る「日本ワイン」を「シャトー・メルシャン」というブランドで1970年から展開しています。
加藤友規(以下加藤):創業140年ですか。我々の会社が創業170年であるのですが、日本ワインの歴史もとても長いのですね。
安蔵:はい。そんな日本ワインの歴史の中でターニングポイントになる時期がありました。その一つが1998年より醸造アドバイザーとして世界的に有名なシャトー・マルゴーの元総支配人であるポール・ポンタリエさんをお招きしたときなんですね。
ポンタリエさんに初めてワインを飲んでいただいたとき、「青い香りがある」「樽の香りが強すぎる」などと淡々としながらも手厳しい指摘をたくさんいただきました。
そして日本ワインが目指すべき方向性を「フィネス&エレガンス(調和のとれた上品な味わい)」と表現してくれました。
加藤:「調和のとれた上品な味わい」とはなかなか捉え方が難しそうです。
安蔵:そうなんです。やわらかく、エレガントに。言葉の意味は理解できても、はじめはその真意が読み取れなかった。するとポンタリエさんは「京都にいい例があるじゃないですか。日本庭園ですよ。あれをお手本としたワインをつくったらいい」と。そのときに日本人なら誰もがイメージの中にある庭園の情景が脳裏に広がりました。

加藤:あぁ。まさに今日お越しいただいた無鄰菴のような庭園ですね。
安蔵:はい。まさにそうです。たとえばフランスのヴェルサイユ宮殿には、巨大なお城があり、その周りには区画され幾何学的に整えられた植え込みや芝生があり、大きな噴水がある。それも庭園です。けれど日本庭園の場合、ひとつひとつの要素はすごく目立つものではないけれど、全体の調和としての完成度がある。そういった日本人にしかできないワインづくりを目指すべき。そんなメッセージだったのだと解釈しています。
「無作為の作意」の言葉に宿る日本庭園と日本ワイン
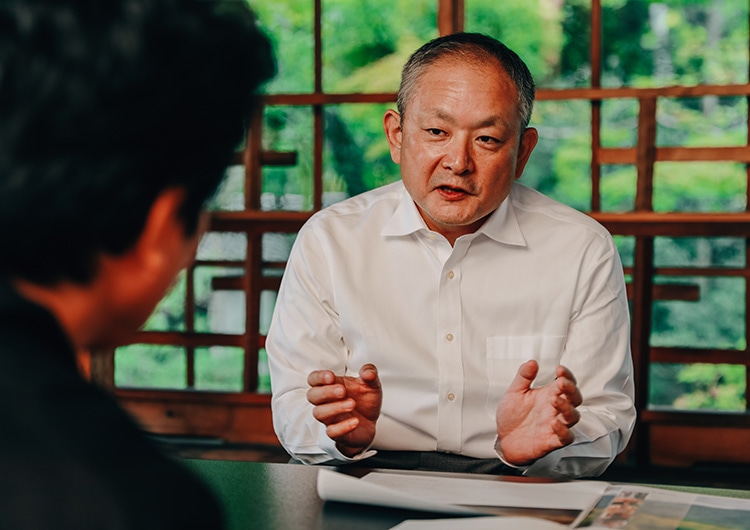
安蔵:そのときのポンタリエ氏のメッセ―ジがこちらです。
グランヴァンは日本庭園に例えることができる。 共に複雑で、深み、調和がある。 日本庭園は、小さなものが集まって、全体に溶け込んでいる。 全て統一がとれ、過剰なものがない。 グランヴァンも、調和、バランスに重点を置いており、 タンニン、アルコール、果実味、酸など全ての要素が混在し、 どれひとつとして支配的なものがない。
こちらのメッセージを見た率直な感想を伺わせてください。
加藤:まず、日本庭園は「主張させない」ことに意識を使います。庭師が想いを込めて手入れをするのですが、謙虚に見せる必要があります。「無作為の作意」なんてよく表現しますけど、庭師の作為が入っていないように見せることが重要なんですね。
よく“ドヤ顔”なんて言いますでしょ。これ見よがしではいけません。庭を訪れた人がいいなと感じてくれ、その人の心の中に庭が残ればいい。そんな姿勢です。ですから、日本庭園が景色の中でこの“ドヤ顔”をしていないように、ワインの味わいの中にも、きっと主張しすぎてはいけないという意味で、ポンタリエさんは日本庭園になぞらえたのかもしれませんね。

安蔵:「無作為の作意」、まさに当時の日本ワインは海外のワインと肩を並べるために作為的になっていたような気がします。たとえば醸造に使用する新樽はとても香りが強いのですが、当時は新樽の香りのあるワインを造ろうと、あえて、すべてこの新樽を使って醸造していました。でも、これがつくり手の「作為」そのものだったわけですね。
“自然に勝とうとしない”考え方

安蔵:ポンタリエさんの言葉の中に「全体に溶け込みながら、一つとして無駄なことがない」という一文があるのですが、庭をつくっていくときは、どんなところに意識を向けているのでしょう?
加藤:昔から一貫しているのは、自然を理解し尊ぶ心を大切にしてきたように思います。作庭を記した平安時代の書物『作庭記』にこんな言葉が登場します。
「人のたてる石は生得の山水にまさるべからず」
解釈するに、庭は自然と人との共同作品であり、自然への深い想いをベースにしてこそ、人の営みに創造性が生まれ命が宿る。人為的につくり出したものでは自然の景色には勝てないということでしょう。
自然に勝ろうとしてはいけないという教えが、1200年近く前から守られてきました。
だから庭師は傲慢になってはいけない。微力な人間の手をいかにして活かすかということを根本理念として持っています。
安蔵:ワインの世界にも共通することがあるように思えます。ワイン造りにおいてよくこんなことが言われます。
「ブドウの出来が9割、人の手が1割」。
すなわち、優れた土壌から生まれた良質なブドウには、人間の手で変えられるものではないということなんです。関われる部分はせいぜい1割なんだという教えです。加藤さんのお話を伺っていて、そこがとても似ているなと感じました。もちろん、この1割をおろそかにすれば、ワインはだめになってしまうので、醸造の立場はとても大事ではあります。
日本庭園を説明するときにはよくワインづくりにたとえます

安蔵:私たちのワインづくりの集大成とも言える、“究極の日本庭園”をコンセプトにした「アイコン・シリーズ」があります。椀子ヴィンヤード、城の平ヴィンヤード、桔梗ヶ原地区、3つの畑から生まれた、日本最高峰のワインだと自負しています。
これらは毎年つくれるわけではなく、特にこの「城の平 オルトゥス」は、1984年から垣根仕立てでカベルネ・ソーヴィニヨンの栽培をしていますが、ブドウの出来不出来がとても激しい。天候が難しい年は瓶詰めを諦めます。本当にいいもの、納得のいくものだけを提供したいという考えからです。
加藤:それぞれのワインに個性があるというのは、ふたつとして同じものがない日本庭園とも共通しますね。気候風土に合わせて、やはりできる庭も違います。
実は、海外の人へ日本庭園の説明をするときには、よくワインづくりにたとえているんです。
安蔵:そうなんですか!?
加藤:はい。庭づくりもワインづくりと同じように、自然と向かいながら景色を育んでいます。そしてこの景色に至るまでに多くの人の情熱と時間が費やされている。そんなことを説明するためにワインづくりを引き合いに出すとイメージが湧きやすいようです。ワインを醸造することと、庭の景色をはぐくむことは、よく似ているんですね。
だから私自身、ワインづくりには興味があってお話を聞いてみたかったんです。今日お話を伺っていてとてもシンパシーを感じています。
安蔵:それはとても嬉しいお話を聞けました。
後編は、日本庭園と日本ワインの未来に向けて、「何を育て」「何を残すか」について語っていきます。
取材協力
無鄰菴(京都市左京区)

国指定名勝の無鄰菴は、明治27年(1894)〜29(1896)年に造営された明治・大正時代の政治家山縣有朋の別荘。庭園は施主有朋の指示に基づいて、七代目小川治兵衛により作庭された近代日本庭園の傑作。南禅寺界隈別荘群の中で唯一通年公開されている庭園で、昭和26年(1951年)に国の名勝に指定される。現在では、庭園コンシェルジュによるガイド(要予約)や、ゆっくりと庭園を味わえるカフェも通年楽しめる。また、様々な日本文化を味わえる講座やイベントも開催中。


